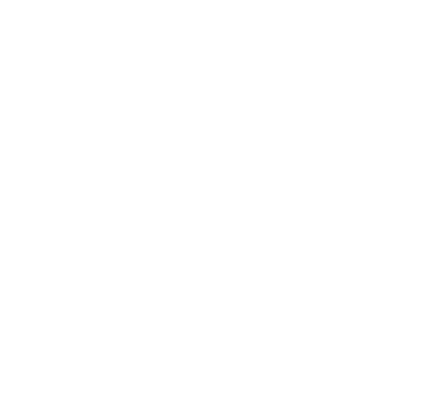タイの国技である格闘技「ムエタイ」。キックボクシングとも呼ばれる。国技であるにも関わらず社会的ステイタスは低い。これは競技が賭博の対象とされており、貧困層のスポーツと見なされているため。貧富の差の激しいタイにおいて、貧しい家庭に生まれた子の資本は自分の肉体のみであり、ムエタイ選手もしくは売春婦になるしか生きていく術がないといわれることすらあるという。
タイ国内に3万人は存在するという15歳未満の児童ムエタイファイター。本作はともに8歳の少女ファイター、スタムとペットを二年間追ったドキュメンタリー作品である。家族の生活を背負った少女たちが願うのは、闘いに勝利し賞金を得ること。
自分の使命は賞金稼ぎであり、お金が家族を幸せにすると信じる少女。日々過酷な訓練を重ねる娘を誇りだと語る父。娘が抱える重い病の治療こそムエタイなのとほほ笑む母親。
賭博に狂乱する大人たちの飛び交う怒号のなか、幼き少女は今日もグローブのみでリングに立ち、互いを傷つけあう。拳の先に、少女たちは何を見つめるのか。
勝者と敗者。骨がぶつかり血が飛び散る激しい闘いに決着が下された時、彼女たちの運命は――。
衝撃的なドキュメンタリー映画である。
原題は"Buffalo Girls"。タイにおけるバッファロー(水牛)は、人のために働く動物として崇められているが、同時にただひたすら人間に奉仕する存在として蔑視されてもいる。おぞましいことに、このタイトルは、本作に登場する少女たちの実態をこのうえなく的確に表していると言えるだろう。
本作がおもにキャメラを向けるのは、2人の少女ムエタイファイターである。
1人はスタム。キャメラの前に立つときの彼女の表情やしぐさは、普通の8歳の少女と何ら変わりはない。
そんなあどけない彼女の口から「お金が欲しい」という言葉が発せられるとき、われわれはいささかたじろぐ。それはもちろん自分たちが暮らす先進国の「常識」が頭にあるためだが、このわずか8歳の少女は、「お金を稼がなければ、(建設中の)家が完成しない」とその理由を明確に語ってみせる。当然そこには「なぜ私がお金を稼がなければならないのか」という反問は介在しない。生活を維持するためには、家族の誰もが自分にできることをして金を稼がなければならないという認識が、スタムのなかで確立されているのだ(そのことは、ラストの彼女の言葉によって、もう一度はっきりと示される)。
スタムの父親は、娘の体が健康なうちはムエタイを続けてほしいと語るが、同時に人生を選ぶ権利は娘自身にあるとも語る。これによって、「判断力にも乏しい子どもにこんなことをさせて……」という私たち観客の先入観にもとづく難詰はみごとに打ち消される。
もう1人の少女、ペットもやはり8歳。彼女は心臓病を患っているが、彼女の母親はムエタイを始めたことで娘は健康になったと語る。また、父親は娘には「闘争心がある」と言う。スタムの両親に比べると、ペットの両親にはよりためらいがない。訓練を積めば危険はない、と語るその笑顔にいつわりは感じられず、子どもたちによるムエタイを純粋にスポーツとして楽しんでいる様子も伝わってくる。
そうした両親の言葉を裏づけるように、ペット自身も「私は強い」という言葉を口にする。彼女にとって、ムエタイは心臓病を患った自分を鼓舞するための「生きがい」なのだろうか。
少女たちの試合風景は、大人のそれと比べても何ら遜色のない壮絶さである。
少しでもモチベーションが下がれば賭け金はグンと減り、闘う気力を見せればグンとはね上がる。試合に負けてしまうと、金を出した観客から容赦ない叱責が浴びせられる。
作中でレフェリーの男性が語っているように、子どもの骨は未発達で大人よりももろい。実際、腕や足の骨を折り、酷い場合には骨が突き出ることもあるという。そう語る彼の目の前には幼い自分の息子がいる。「息子さんにはムエタイを?」と問われた彼は「ケガが心配だからやらせない」と答える。
このような大人たちを「身勝手」「人でなし」と非難することは容易い。私たちは昔からディズニー映画や世界名作劇場による「情操教育」を通じて、子どもを金のために「見世物」にする大人たちを目にしてきた。そういう大人は例外なく、悪役として描かれていたはずだ。しかし、そのような一面的な視点が先進国の思いあがりでしかないことを、私たちは本作が映し出す現実を目の当たりにしてあらためて知るだろう。子どもに試合をさせて金を稼がせる親たちにも、またそういう場を提供する大人たちにも、それぞれの価値観があり、生活がある。それを異なる文化圏にいるわれわれが一概に非難したところで、問題の本質は何ひとつ見えてこないのだ。
それでも、やはり私たちには、この映画に記録されている少女たちの試合風景を「勝つのはどちらか」という視線で見守ることはできない。いつ取り返しのつかない怪我を負うかもしれない、その緊張感だけが私たちに画面を凝視させる。
それはやはりこの映画が「外部の目」で撮られていることの証である。そもそも本作に登場する「闘う少女たち」の実態は、「外部の目」が介在することにより、初めて私たちの問題として浮上するのではないか。監督トッド・キールスティンは、ナレーションや字幕で問題をあげつらうするような真似はせず、撮られた映像を提示して、観る者にじっくりと省察をせまる。
彼女たちには帰るべき家があり、帰属すべき場所がある。そのことを明示して本作は静かに幕を閉じる。どんなに過酷な現実が横たわっていようと、私たちは「外部の目」でそこを酷い場所だと断定することができるだろうか。この映画は、そんなメッセージを私たちに投げかけているような気がしてならない。
文/佐野亨
監督:トッド・キールスティン
ミュージックビデオのクルーとして映像界に入る。
ボン・ジョビやオアシス、ブリトニー・スピアーズなど、数々の大物著名人の作品にディレクターやカメラマンとして参加。その後アディダスなどのコマーシャル制作を手掛けつつ、独自の目線にドキュメンタリー映像を制作。本作がドキュメンタリー長編デビュー作となる。本作は各国の映画祭で話題を呼び、世界中の観客やメディアから絶賛されている。